あなたに出会えたことに感謝します。🙏
こんにちは!ややまる。です!🙌
塩二郎さんのおかげでプレイヤーとして物事を極める上で足りないものについて考える時間ができました。
日常的に足りないと常に思っているのは、集中力だなと思うのです。
子供の頃はただ夢中になるだけだったけど、仕事をするようになってマイナスな感情や不安に晒されてしまう生活を過ごすうちに、どんどん自分への自信を無くしていっていたのかもなと感じました。
塩二郎さんやリスペクトしている友人を見るとただその瞬間を楽しんでいる。
だからどんなことでもただフラットに夢中でいる状態、つまりフロー状態になる方法を知って、みにつけたいと思いました。🙌

今回はメンタルトレーニングを専門とするドクターの辻秀一さんの著書「ゾーンに入る技術」という本から学んだことと実際に実践している事を紹介します!👍
フロー状態とは
フロー状態とはどういう状態のことをいうのか。
本書では「パフォーマンスの質が高い時の心の状態」と紹介されています。
そしてその心の状態を生み出すために欠かせないのが集中力ということをいっています。
著者の中でこの集中には広義の集中と狭義の集中として次のようにいっています。
広義の集中
▶️「何をするのか」が明確かつ正確で(認知脳)、「どうやって」という心の状態(ライフスキル脳)がフローであり、両者のバランスが整っていること(バイブレイン)。
狭義の集中
▶️心の状態が限りなくフロー状態であること。
認知脳、ライフスキル脳、バイブレインについては以下の通り説明しています。
認知脳とは、(略)外部の状況や出来事を判断して、「すること」を明確にする脳である。パフォーマンスの「何をするのか」の部分を支える重要な脳だ。
(中略)
ライフスキル脳は、(略)心の状態を「揺らがず」「とらわれず」のフロー状態にしてくれる。どちらかと言うと内側の、心の状態に向けた脳の働きである。
(中略)
つまり集中状態はこの2つの脳機能がバランスよく働いているバイブレインという集中脳によってもたらされているのである。本書より引用
フロー状態って心の状態なのだということを初めて知りました。
ずっと頭の状態なのかなと思っていたのですが、おそらく認知脳とごっちゃになっていたのだなと気づきました。
目指すところはわかったので、次はなぜ集中が続かない状態が起こっているのかを見ていきます。
なぜ集中できないのか
フロー状態の定義は理解できましたが、なぜ集中力が切れてしまうのかを知る必要があります。
本書では気が散って集中できていない心の状態をノンフロー状態といっています。
そしてこのノンフロー状態とは「揺らぎ」「とらわれ」の状態を指していると著者はいいます。
揺らぎととらわれは、本文で以下の状態だと紹介しています。
「揺らぎ」とはさまざまなマイナス感情が想い起こされた不安定な心の状態のことである。
「とらわれ」とは過去の出来事から作られた潜在意識の中に形成された、思い込みに支配された状態である。本書より引用
そしてこれは脳の仕組みが原因なのだというのです。
脳は勝手に意味づけを始めていき、それが揺らぎやとらわれを自分の中で起こしているというのです。

言われてみると日常や人間関係での不安要素や過去の経験のせいで何も手につかないということがあったので納得です。💧
著者は「まず気が散る原因は脳の意味づけによって起こっていることに気づくこと」が大事だといっています。
いわゆるメタ認知と呼ばれるものに近そうです。
メタ認知とは、ざっくりいうと「自分がどんなことを考えて、どんな行動しているかを、客観的に把握して、理解して、調整すること。」です。
ただ認知脳による意味づけは生きている以上影響を受けるので、いくらメタ認知をしても簡単には変わるものではないと指摘しています。
そこで著者は認知脳よりもライフスキル脳を磨く方が簡単だという話をしていました。
なので次は実際にライフスキル脳を磨く方法について見ていきます。
ライフスキル脳を磨く3原則
ライフスキル脳を磨くには3原則があり、それは「知識」「実践」「シェア」だと書かれています。
知識
知識とはライフスキル脳の仕組みやライフスキルとはどんなものなのか、フローとは何か、なぜ人はノンフロー状態になるのか、という知識です。
これらをより詳しく知ることがまずライフスキル脳を磨く基本だといいます。
ただ脳の機能上忘れてしまうのも事実。なので繰り返し復習して忘れない仕組みづくりが大事になっていきます。
実践
実践とは知識で知ったことを実践することです。
知って終わりではもちろん身につかないですし、何より実践しないとフロー状態を感じることができないからです。
また実践することで知識を忘れない仕組みづくりの助けになります。
シェア
実践で得たフローの感覚をご褒美として脳に刷り込ませるために、人に言葉で分かち合う、つまりシェアが大切なのだといいます。
著者はこの原則の重要性を伝えると同時に、これが敷居を上げているせいで身につかないことを指摘しています。
だからライフスタイル脳について知ったことを実践して人に伝えることを繰り返すという感じでしょうか。

昨今SNSもあるので、他者への発信のハードルは下がっているのでやりやすいと思います。私もブログという形でシェアを意識しています。ただ夫や友人に声で伝えるのも効果的かもですね!🙌
実生活においてフロー状態にする工夫
ここからは本を読んでこれは!と思って実践したことを紹介します!✨
好きなもののことを考えてから作業を始める
これ私には即効性がありました。
それこそ仕事でルーティンワークをやる時に、やらないと終わらないのはわかっているけどスイッチが入らない。。そういう時に好きなもののことを考えるとフローに入りやすいとのことでした。
ちなみに私、あんこが好きなんです。(急)
おはぎも好きですし、あんパンも好きですし、小豆仲間で考えるならようかんも好きです。
それでルーティンワークの前におはぎを想像したり、あんパンを想像したりしてました。
するとやらなきゃいけないことに対する気持ちがマイナスな感情じゃなくて、無というんでしょうか、余計な感情がなくなってできるようになりました。🙌
結構おすすめです!
人も自分もリスペクトを持って応援する
リスペクトというは尊敬ではなく尊重の意味として本書ではいっています。
尊敬だと自分と相手を比べる、つまり外部の出来事に対しての言葉になるので認知脳の領域になるのだそう。
確かに尊敬とは自分より相手を上に見て無意識に比べている言葉だなと改めて思います。
ライフスキル脳は内側の気持ちが重要です。
なので相手も自分も尊重する。そしてそれぞれがしたいことを応援する。
尊重と応援もフローに入るために有効な方法だとあり、こちらはすぐにはできないですが意識するようにしています。
自分のために感謝の気持ちで行動する
個人的には感謝の気持ちが大事だよという考え方の答えになっていると思っています。
よく感謝の気持ちを持ちましょう!というのは言われるけど、表面的というか心をこめていっていない感じがしませんか?少なくとも自分はそう感じることは多々ありました。
でも感謝の気持ちがあるからスポーツ選手をはじめ、様々な競技の人が最高のパフォーマンスを発揮できることが研究でわかってきたとありました。
つまり人への感謝を通して、自分のために感謝をするんです。
やってみて思うんですが、自分のどんなことにも「ありがたい」と思うと余計なマイナス感情が湧かないんですよね。
湧いたとしてもすぐ落ち着くといいますか。
感情も複数の感情を同時に持つことができなんだと改めて感じました。🙌
あんこの食べ物を浮かべながら並行してやってます。🙌
まとめ:理屈は抜きで心の動きを重視する
「こういうのって理屈をつけないとできない人がいるのですが、まずは理屈抜きでやってほしい。」と著者はいっていました。
著者は本書でも繰り返しいっていましたが、ライフスキル脳は心の状態だと、そして心の状態に理屈は関係ないという話をいっていました。
理屈=意味づけは認知脳の機能だからといっています。
これは長年の習慣もあると思うのですが、理屈はわからんけどとりあえずやってみるかという状態を意識することもライフスキル脳に繋がるからだと思います。
とはいえ、認知脳も大事でただ認知脳を意識するのは「何をするのか」という明確な目標で、「どうやって」の心の状態をライフスキル脳に任せてバランスよくやるということを意識してほしいといっていました。
他にも紹介できていないことがありますが、読み応えのある一冊なのでぜひ読んでみてくださいませ!📕
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!🌼
またお会いしましょう!🌱
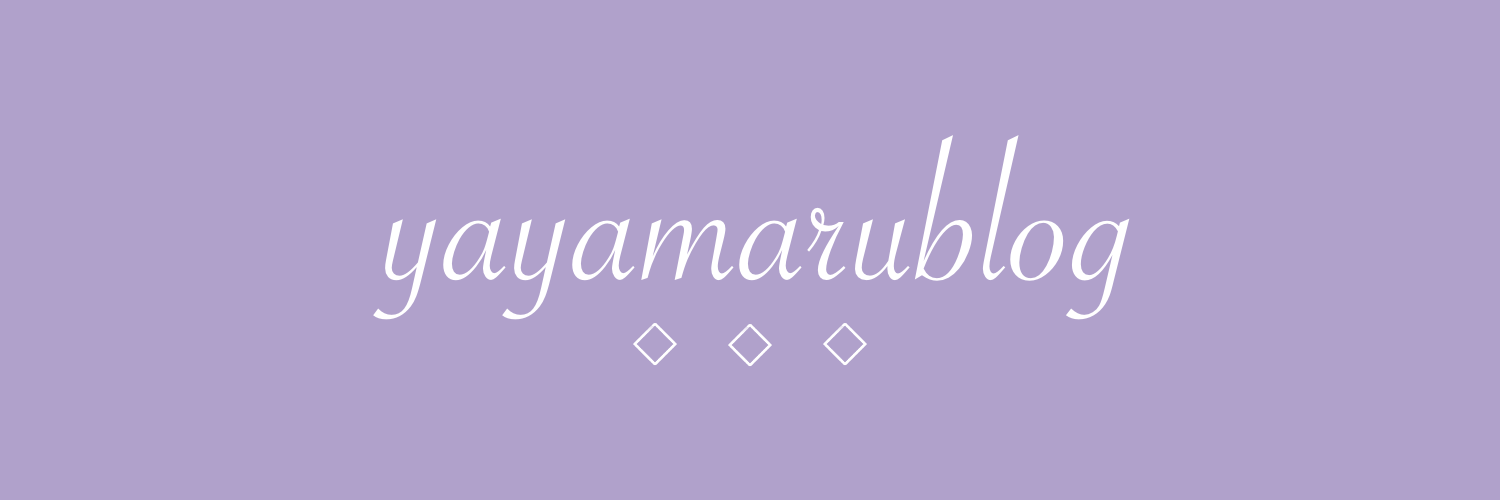
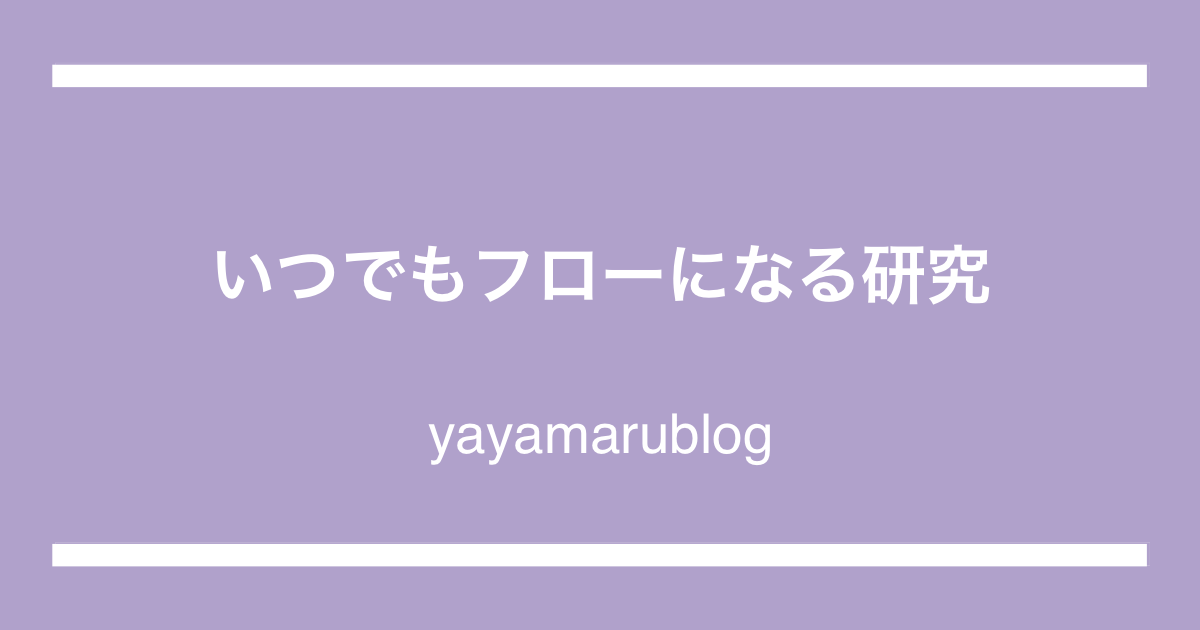


コメント