あなたに出会えたことに感謝します。🙏
こんにちは!ややまる。です!🙌
夫と日々いろんなアニメを見ていますが、やはり作品によってはそのキャラクターの身に起こる事件に触れなくてはいけない場合もあります。
中でも強烈なのはキャラクターの「死」ではないかと思います。
私はキャラクターの「死」から得られる価値観について考えることが好きです。

本日はそんなキャラクターの死についての私の考えについて語りたいと思います。
推しの死が耐えられない人と出会う
「この間、最新話で私の推しキャラが死んでしまって。。今めっちゃ気分が落ち込んでるんです。。。」
昔働いていた塾の生徒があまりにも元気がないので、どうしたのかを聞いたらこのように答えていました。
当時、鬼滅の刃が連載時で、X(旧Twitter)でも「鬼滅の刃は推しが死ぬ作品だ」といわれるほどでした。
月曜日にはお通夜の状態の人が何人もタイムラインで流れるなど結構この生徒の話は印象に残っています。
ただ、私はアニメを見るときに感情移入よりもその物語を考える人の視点で見ることが多いので、推しが死んで辛いというのはあまりなかったです。

書いてて思いますが、だいぶドライすぎると思います。笑
ただここはめっちゃ強調したいのですが、ちゃんとアニメを楽しんでいるので、いざキャラクターの死を目の当たりにするとめっちゃ悲しいんです。
でもそれ以上に、なぜ彼らは死ななければいけなかったのかを考えることに興味関心が移るためです。
生きていることで物語が面白く無くなる
なぜ死ぬ必要があったのかについて、私はそのキャラクターが死んでからが作品の面白さが引き立つからだと思っています。
自分でも冷めた見方だなとは思うのですが、感情は抜きにしてアニメの演出として考える必要があります。
物語を作る視点からすると、死んでしまうキャラクターって、そのキャラクターさえいれば主人公いらんやろっていうほどのバランスブレイカーになっていたりします。
こうなると主人公の成長の妨げでしかなくなるので、どっかで遠くに行ってもらう必要が出てきます。
あくまでも主人公視点での脇役に過ぎないので、主人公が前に進むための障害になるのであれば遠慮なく「死」を描くのかなと考えています。

あまりにも強力な力を持っている人物や主人公の師匠筋など、何かしら主人公より優れている存在は乗り越える壁として早々に退場してもらうか死んでしまう傾向があるなと見てておもいます。
どこまでも主人公軸がブレないようにするのが物語なので。。
マルチバースの概念で「死」も可能性の一つに
ただ最近は「死」で終わるという流れから、「死」から始まる作品も増えてきているように感じます。
代表的なものが「異世界転生」系の作品だと思います。
そして同じ作品でも「死」でおわったと思ったら実は生きているという違う展開のものがあったりと、死というものが決定づけられた運命ではなく、可能性の一つになっているなと思います。
ゲームのマルチエンディングの概念がこれにあたると思います。
なんだこんなにマルチバースが人気になったのか。
これは私の考察ですが、「死」という強烈な出来事を重く受け止めすぎないようにする意図があると思っています。
人はいつか死んでしまうのは皆さんわかっているし、いざ「死」というと怖いものだなと思う人が大半だと思います。
けれども、そういう「死」について恐れすぎては生きづらくなります。
だから「死」の先を描くことで、「死」そのものに対して適切に怖がるように自分でコントロールしているのかもしれません。
私は一種の防衛の面でマルチバースの考え方があると思っています。
まとめ:キャラクターの「死」から現実の「生」を考える
改めて、なぜ「死」を意識するのかというと、生き方を見直すきっかけになるからではないかと思っています。
死んだ人の思いを生きている人がきちんと継承していくのは、アニメでなくても現実世界でも大切なのは変わらないですから。
それを踏まえて、今の人生って後悔なく生きていると胸を張って言えるだろうかを考えるきっかけになると思っています。
本日の話のテーマは浦澄彬さんの著書「なぜあのキャラは死ななければならなかったのか」を読んで着想を得ました。
こちらは1970年代から令和に至るまでのアニメキャラの「死」から社会情勢を見るという切り口の本です。
ただ情報としては歴史を追うにはちょうどいいですが、「死」に対する考え方についてはあまり深く言及されてはいない印象です。
それこそ読んだ読者への考察に委ねているのかなという印象です。
ご興味がある方は読んでいただけばと思います!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!🌼
またお会いしましょう!🌱
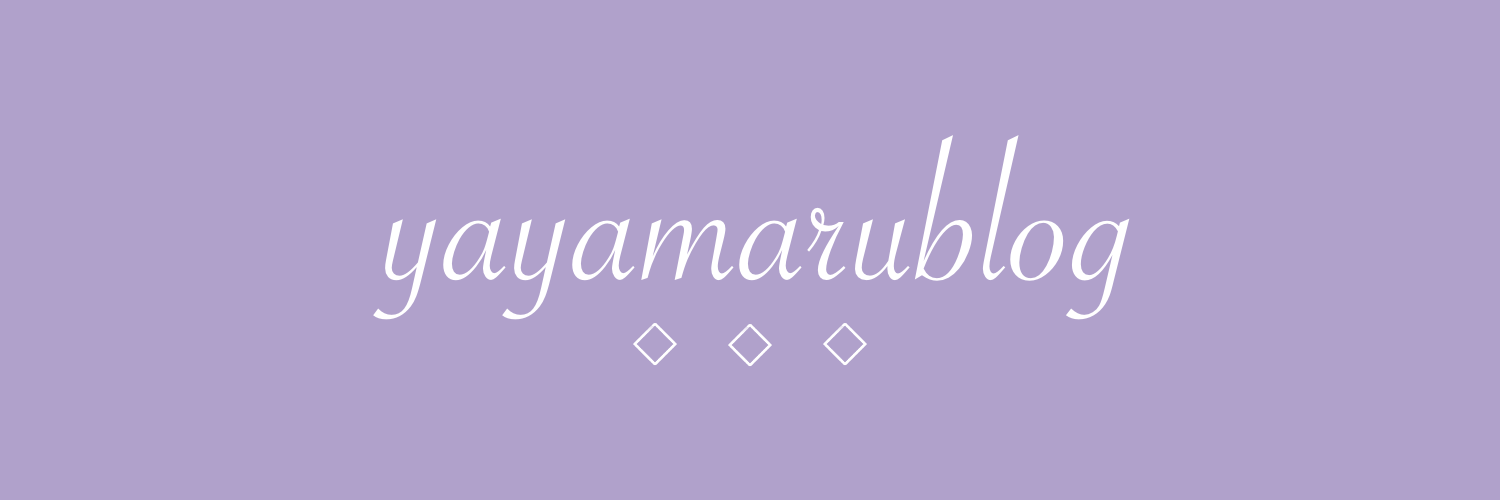
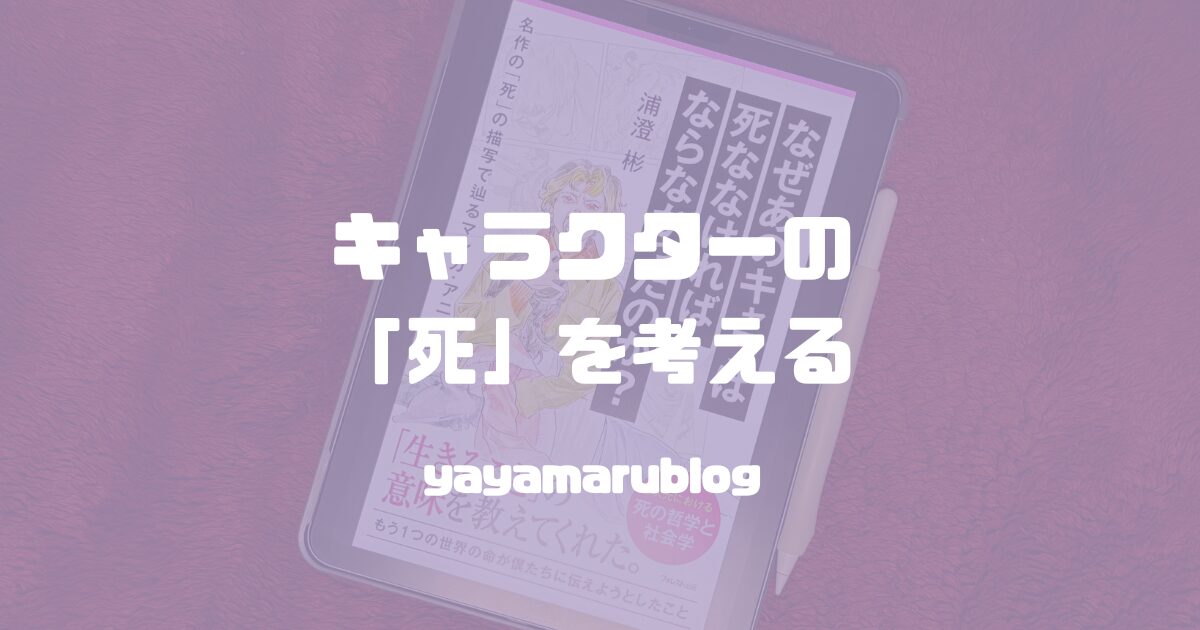


コメント