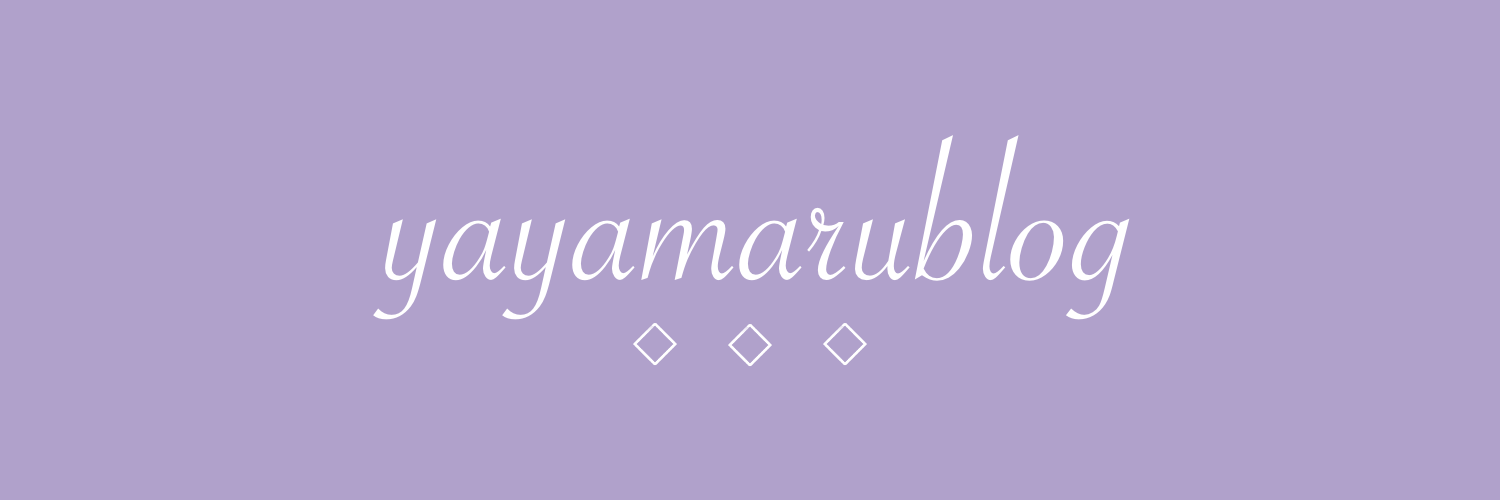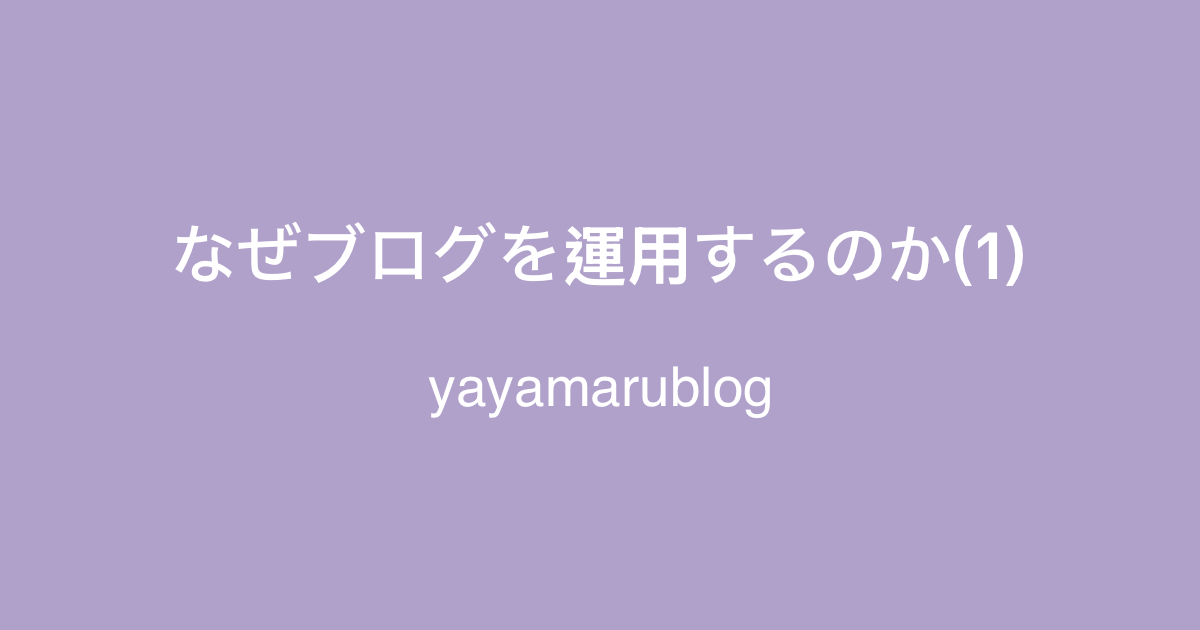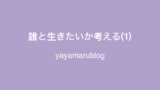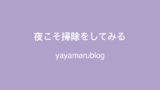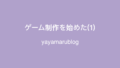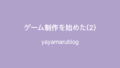あなたに出会えたことに感謝します。
こんにちは!ややまる。です!
先日紹介させていただいた、君は誰と生きるかに実は続編がありまして。
君は誰と生きるかの紹介記事はこちら↓
続編のタイトルは「君はなぜ働くのか」という本です。
ふと、この本を読み返した方がいいという直感が働いて読み返していたのですが、まさにリスタートした今だからこそ必要なことを思い出ました。
・なんかブログのモチベが下がりそう
・何でブログを書き始めたんだっけ
と思ったときに背中を押せるよう、記事にしようと思います。
もちろんブログに限らず、お仕事や生活に通ずるものがあるので参考になると思います。
モチベーションの正体
この本では、人は「なぜ」の中にある意味が重要で、なぜの中にある意味を見つけられれば前に進める、これがモチベーションの正体だというのです。
自分は何をやるのか、誰と生きるのか、どのようにやるのかってことは、この『なぜ』の部分が明確になっていないと簡単にダメになっちゃうんだ
本文一部抜粋
物事を始めるきっかけはなぜそれをしようと思ったのかが、軸にあるなと確かに思いました。
それを踏まえてなぜブログを始めたのかを振り返りました。
ひとつは今までの自分を変えたいと思ったからです。
儲けようじゃなくて、変わりたいんだと振り返って気づきました。
わたしは虚弱体質であることを何度かブログで触れましたが、今までの自分は諦める理由を体質のせいにしてきました。でも本当の自分はいろんなことにチャレンジしたい、だからこの虚弱体質と真剣に向き合うタイミングが来たんだと思いました。
5分リストも習慣化の意味がありますが、体調が良くなくてもできる時間だから言い訳しないようにするためでもあります。
もしかすると、なんか続けられなくなってしまうのは根底にある「なぜ」の部分が本音とずれてしまっているのかもしれないですね。。
5分リストの話は以下の記事もご参照ください!
好きなことを仕事にする前にやること
本文のこの一節はブログを進める上で大事だなと改めて気づきました。
まずは『自分が仕事を好きになること』。次が『仕事に好かれる自分になること』。この順番だよ。
本文一部抜粋
この一節をブログに当てはめるのなら、まずは『自分がブログを好きになること』が最優先で、突き詰めていくと、人から頼まれ事が増えて『ブログに好かれる自分になる』という事になるでしょうか。
毎日ブログに触れる重要性って習慣もあるんですが、前提としてブログを好きになるためでもあるのかなと思います。
結構ブログ書くの、時間がかかりますよね。
でも好きになればブログの更新作業も楽しめます。
現に毎日更新していますが、確かにブログにまつわることは好きになってきたので、引き続きブログを好きになれるように毎日更新を続けていきます。
先に好きになっていけば、本当に好きなことを仕事にしている事になりますもんね。
松下幸之助さんの素敵な話
本では仕事の意味を見つける例として、松下幸之助さんの話を紹介しているのですが、その話がもう一つの私のなぜの根幹にあります。
ちなみに松下幸之助さんはパナソニックホールディングスを一代で築き上げた経営者です。
ある日松下さんが、工場内を見ているときにつまらなそうに電球を磨いている若者を見つけて話しかけるんですが、その若者は何のために電球を磨いているかわからないと松下さんに言いました。
その時に松下さんは彼にこう言いました。
『それは、君が電球を磨くっていう作業ばかりにフォーカスしているからや。そうやなくて、もうちょっと向こうを考えてみ。この電球があるから、家族が楽しく過ごすことができる。この電球があるから、人が本を読むことができる。この電球があるから、世の中の人々が暗闇に怯えることなく楽しく過ごすことができる。そう考えたとき、君が磨いているのは電球やない。人々の幸せを磨いてるんや』
本文の形式で抜粋
この話が本当に好きです。働く意味がわかるとモチベが変わるいい例ですよね。
私のもう一つのブログの根底にある「なぜ」はブログを通して元気を届けたいからなんですよね。
虚弱体質の私のチャレンジが同じような境遇の人の元気につながるなら、私が持ってる力で元気になれるようにできる事に向き合おうと思って毎日ブログを書いています。
私自身がエンタメみたいなものです。私が何かにチャレンジしている姿をみて一歩踏み出す勇気になればいいなと思っています。
また別記事にしようと思っていますが、占い的にも私がエンタメになることが吉だと出ていたので、この気持ちを忘れずに続けていこうと思います。
まとめ
今回は自分の根底にある「なぜ」が大切だという話をしました。
皆様も手が止まった時に、自分の中の「なぜ」と本音を見直して、ブログの向こう側で誰かの力になっていることを知るというのもいいかもしれないですね!
まだまだ紹介したいことがあるので、また別記事でこちらの本のことを書きますね!
ここまで読んでいただきありがとうございました!
また会いましょう!