あなたに出会えたことに感謝します。🙏
こんにちは!ややまる。です!🙌
昔から神話が好きでして、ふと神道のことを知りたいなと思いました。
仏教とは違う気質じゃないですか、神道って。
決まった教えはないのに日本では当たり前のように根付いている感覚は、改めて考えると不思議だなと思ったんです。
そこで島田 裕巳さんの「【増補版】神道はなぜ教えがないのか」という本から神道に対する不思議な感覚について感じたことを書いていきます。🙌

あくまで神道についての知見を述べるだけですので、他宗教への批判等ではないことをご承知いただければと思います。
「ない宗教」といわれる神道
こういった宗教の話などを触れる機会が多い人にとって、神道は「ない宗教」と呼ばれていることはご存知かもしれません。
そしてこの「ない」ものが多いゆえに、宗教としてはあまりにもシンプルな構造になっていると本書ではいいます。
後述しますが、神道には教祖はいませんし、救済の要素は欠けているというのです。
考えてみれば、神道は仏教やキリスト教のような信仰のようなものって感じないなとは思ったんですよね。
なんだろう、あまりにも自由で余白があるイメージがあります。
本書でも仏教やキリスト教のような「ある宗教」との共存が可能だったのは、神道の持つ自由さが大きいからだといいます。

お正月があったり、お盆があったり、クリスマスがあったり、思えば宗教に関わるイベントがごっちゃになってますもんね。
異宗教であっても神道的には多様性を重視するということなのかもしれませんね。🧐
神道は教祖はいない
本書で教えがない理由として、そもそも教祖のような自らの教えを説く存在がいないことが挙げられています。
仏教でもキリスト教でも、明確に教祖という存在はあるのに確かに神道の開祖は誰ですかと言われても、いつの間にかあったからわからないというのが答えなような気がします。
それこそ神道といえば八百万の神さまといって神様は身近にいてたくさんいるという考え方があります。
これも教祖はいないのに、なぜか知っていたり、知らなくても親であったり友人であったりから「モノにも神様がいる」って聞いた方も多いと思います。
私の場合は父が祈祷師なのもあり、神道の考え方に触れる機会が多かったのも大きいですが、「なぜ神様はたくさんいるのか」という話の起源は不明です。
でもいろんな形で神様がいるという考え方は個人的には大好きだったりします。

江戸時代から続くリサイクル精神の柱である「勿体無い」という気持ちも、神道的視点で見れば「形を変えても命は続く」と考えられそうでロマンがありますね。🙌
神道の救済は曖昧
そして極め付けは仏教やキリスト教のように「ある宗教」であれば救済の側面があるはずですが、神道は救済について曖昧になっているのも不思議なポイントです。
家内安全や合格祈願など願掛けはすれど、したからといって神様はあなたをお救いになるなんてことはないってなんとなくわかってたりします。
そもそも神頼みはしても根本的に神様への救いを求めてはいないと本書ではいっていましが、これはよく思います。
もちろん「神様応援してくれ〜」といい結果を望むことはありますが、結局のところ自分たちの力で大体のことは解決できるじゃんって気づいて動いていたりします。
少なくとも私はそうです。
本書では救わないからこそ自分の過剰な欲求に気づくよう促しているのかもしれないといっていましたが、まさにピンチの時こそ自分のことを冷静に見たらちゃんと原因がわかった、なんてことがしょっちゅうあります。

もしかしたら、人間そのものの力を信じることが神道のあり方なのかもしれないと私は考えています。
まとめ:神道のシンプルさが「ある宗教」との共存を実現
初めの方でもお伝えしましたが、日本には仏教もキリスト教もその他宗教にまつわるイベントが暦に含まれていて、私たちの日常になっています。
「ある宗教」にはそれぞれ教えや救済が前提にあるけれども、「ある宗教」同士では悲しいことに戦争にまで発展してしまうこともあります。
でも神道には教えも救済もないゆえに、それぞれの「ある宗教」に干渉せず、共存できるって改めてすごいですし、不思議な宗教だなと思います。
神道を信仰しろということではないですが、「ない」からこそ自分の生き方に舵を取るという考え方は大切なのかなというのを読みながら考えました。
神道という宗教についての著者の知見や歴史について詳しく語られていますので、
興味があればぜひ本書も読んでみていただければと思います!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!🌼
またお会いしましょう!🌱
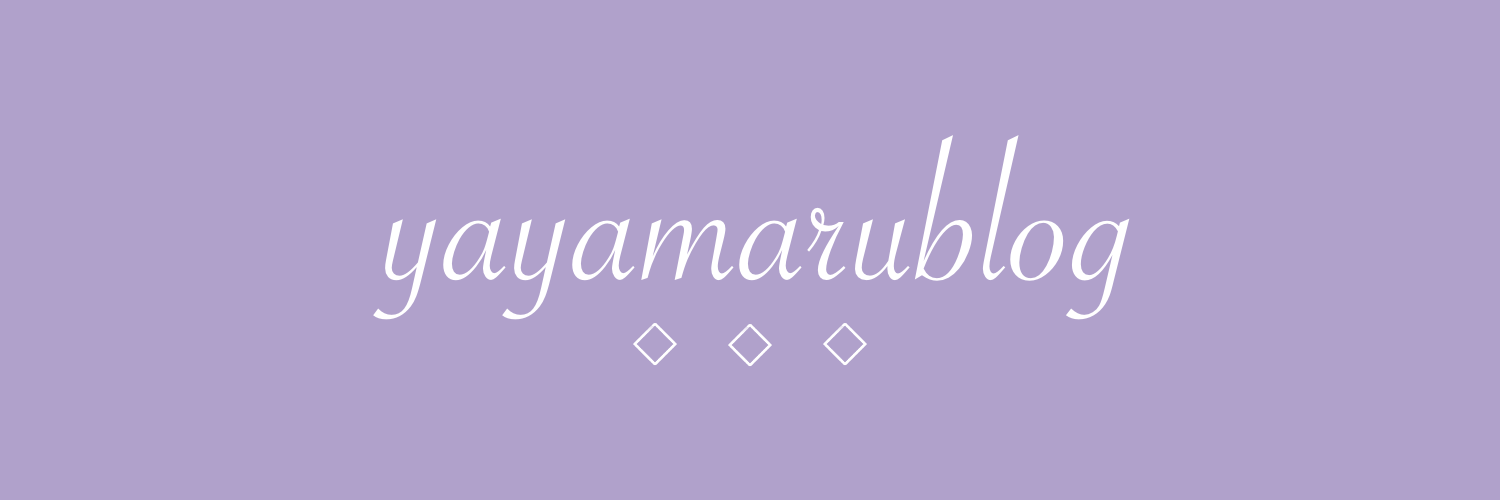
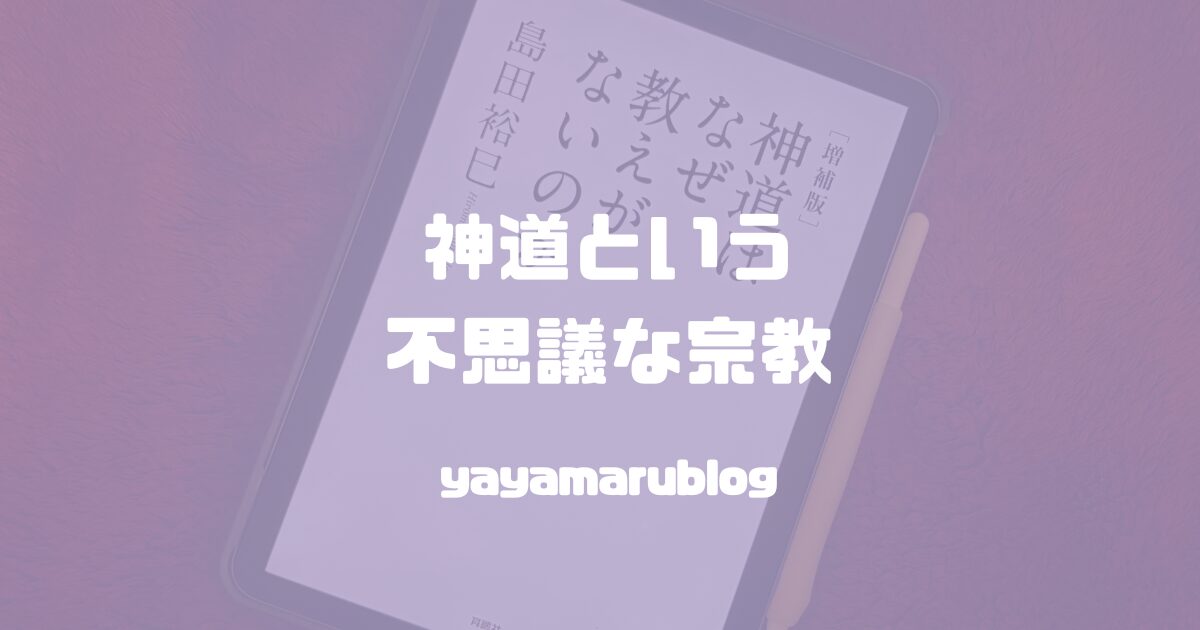
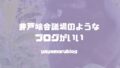
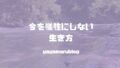
コメント