あなたに出会えたことに感謝します。🙏
こんにちは!ややまる。です!🙌
日々のジャーナリングで毎度共通の結論としていわゆる一般的とされること、つまり世の中のセオリーは捨てようってことでいつも落ち着くことに気がつきました。
もちろん参考になることもあるんですが、わたしの場合はかえって首を絞めてしまって行動できないのかも?と思うことが多く感じます。

今回の話はあくまでわたしの中で通じる理屈なので本当に参考程度で見ていただければと思います。👊
なんか自分に合わない感覚
何かを始めるにあたってどういう風に進めるのか、自分に適切な情報がないと思っていたので手当たり次第やっていました。
もちろんいくつかは参考になると思って続いているものもありますが、ほとんどはやってみて自分に合わないなって思うことが多く、いろんなチャレンジの挫折に繋がっていました。
例えば最近の話だと、英語の勉強のやり方でものすごく振り回されていました。
「こういう風に勉強すると身につくよ。」
「勉強の王道はこれだ!」
などなど。💧
一般的にこうするのがいいというのをまずは情報として仕入れていく。コレ自体は大切だと思っているので全く後悔はしていません。
が、どうにも続けるのがしんどくなっていく感覚がずっと拭えませんでした。
失敗の言い訳探しになっていた
でも、いろんなやり方をやってみて、その時の感情を分析するとあることに気づきました。
私は一般的な正しいやり方や正解を追い求めていました。
自分以外に明確な基準が欲しいなって思っていました。
例えばこの勉強を続けて実際に海外で役に立ったとか、このやり方以外は勉強の効果は発揮されないとか、そういう成功につながった方法を正しいとして扱っていました。
どんなにやりづらくても、コレが正解だからと楽しくないけどやってました。
結果はわかる通り、全然続かなかったです。
でもなんでこんなに正しさに振り回されているんだろうと考えてみると、自分の中の完璧主義が失敗を極度に恐れているなというところまで辿り着きました。
失敗を恐れるということは、自分の選択の責任を自分で持ちたくないということに繋がっているのかもと思いました。
つまり他者のやり方にしがみついていれば、失敗しても言い訳ができます。
「そもそも私に合わなかったからやめたんだ」と。
これだと思いました。
勉強の本来の目的はその勉強した内容を活かしたいからするものなのに、いつの間にか止めるための言い訳にすり替わっていたんです。
本音は嫌なのに、他者のやり方に言い訳をするためにやっていたらしんどいだけで続きません。
ここにようやくたどり着くことができました。
私のセオリーが常識に合っていなくていい
人に責任転嫁するようなやり方でやってたらいつまで経ってもやらなくなるなと思ったので、人のやり方の研究は辞めました。
長年やってきたのでそれなりにノウハウが蓄えられているし、大体のノウハウは見てきたものが多いなという印象もあり、スパッとやめられました。
その代わり非効率でもいいので、自分の中でこう思う!という気持ちを大事にやり方を組み立てていくことにしました。
それで冒頭にもたどり着いた通り、私は世の中で言われているセオリーをガン無視することにしました。
具体的にどうやって無視するのかというと、
例えば
「試験勉強が目的なら毎日2時間を勉強時間に当てましょう。」
というセオリーがあったとしたら、
「試験勉強目的を捨てて毎日5分は1単元のページを読もう、理解はしなくていい。」
という形にします。
するとできなかったことがちゃんとできるようになりました。
重い腰を上げてやらないでいいという気持ちで気がついたら自分からやれる仕組みに辿り着いていました。
こんな感じで実践していることの一部をまとめました。
勉強しようとしない
まず勉強しようとしないことにしました。
厳密にいうと、勉強しよう!って気合いを入れてやらないということです。
気合い入れてやったら疲れるからです。
私の場合は心身ともに時間をかけるのは大きな負担だったのは小さな頃から変わっていないことを思い出しました。
そこで受験勉強や資格試験でよく聞く、何時間勉強しなくてはいけないというのは無視して短時間でこなすというスタンスにしました。
勉強していて気づいたら1時間とかならOKですが、1時間やるという縛りはしてないです。
5分で終わる日もあります。
でもこのおかげで余計な力が入らなくなり、勉強しやすくなり理解力も深まったように思います。
あとは考えたり予測したりしながら勉強するのが好きなので、コーネル式メソッドを活用しています。
ここだけはベストな形が色々調べた結果コーネル式メソッドだったので採用しています。
理解よりやるか否かを優先で
そして理解することよりもやらないことの方がメンタルにくるということがわかりました。
これは行動のハードルを下げることも目的としていますが、自分の理解できる容量が少ないのに無理しようとして潰れていたことを踏まえ、まずは行動したかどうかに絞ることにしました。
ちなみに一つの活動で自分が理解できる範囲って20%くらいだと思っています。
どんなな頑張っても一目見て100%理解しようとするとめっちゃ疲れます。
なので思ってるより許容量は少ないくらいだと見積もっています。
また理解を目的にすると、時間がかかります。
時間をかけると心身の負担が多いだけじゃなく、続けることも難しくなります。
そしてどんどんやらなくなって積み上がっていくタスク。
このタスクから逃げるために現実逃避が癖になっているのは目に見えています。
だから理解より行動したかしてないかを重視しています。
英語の勉強についてはまずはラジオを再生して聞き流してOKくらいでしています。
行動回数を増やして単純計算で5回そのものに触れれば理解できるわけですからやればいいという理屈です。
昔から一回きっかけができると勝手に理解に進むように動く性質があるのできっかけ作りが大事だと気づけました。

こんな感じで基本的にはそれでいいの?ってくらい自分にゆるいルールにしていきます。
まとめ:自分でたどり着くことが大事
多分どんなにセオリーを捨てたとしても、結果として一般的なセオリー通りのことをやっているのだろうなと思います。
でも他者のやり方をそのまま真似するだけじゃなくて、自分で考えて結果としてセオリーにたどり着くことに意味があるように思います。
そこに自分がちゃんと積極的に参加して考えたという実績の積み上げが大事で、この積み上げが自分の自信につながっていくように思います。
おそらく今まで何かを続けられなかったのは他者のやり方を自分に合わないままでやっていたからなのかもしれないと考えるきっかけになったという話でした。
皆様も一旦世間で正しいとされていることが自分に合わないかもと疑ってみると面白い発見があるかもしれません。🙌
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!🌼
またお会いしましょう!🌱
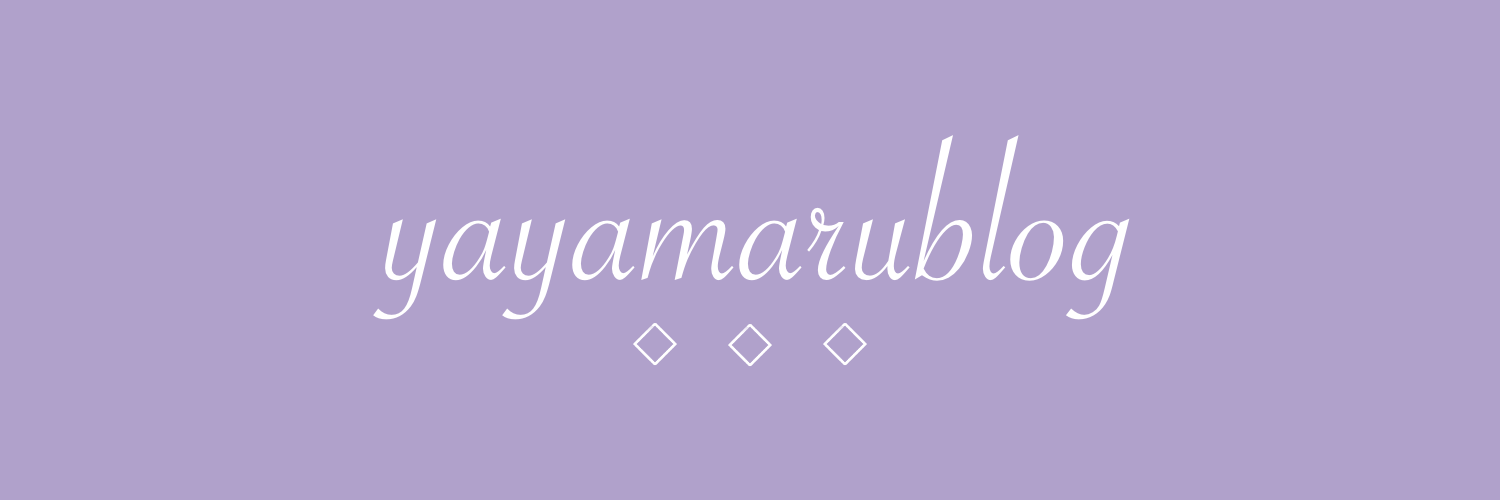
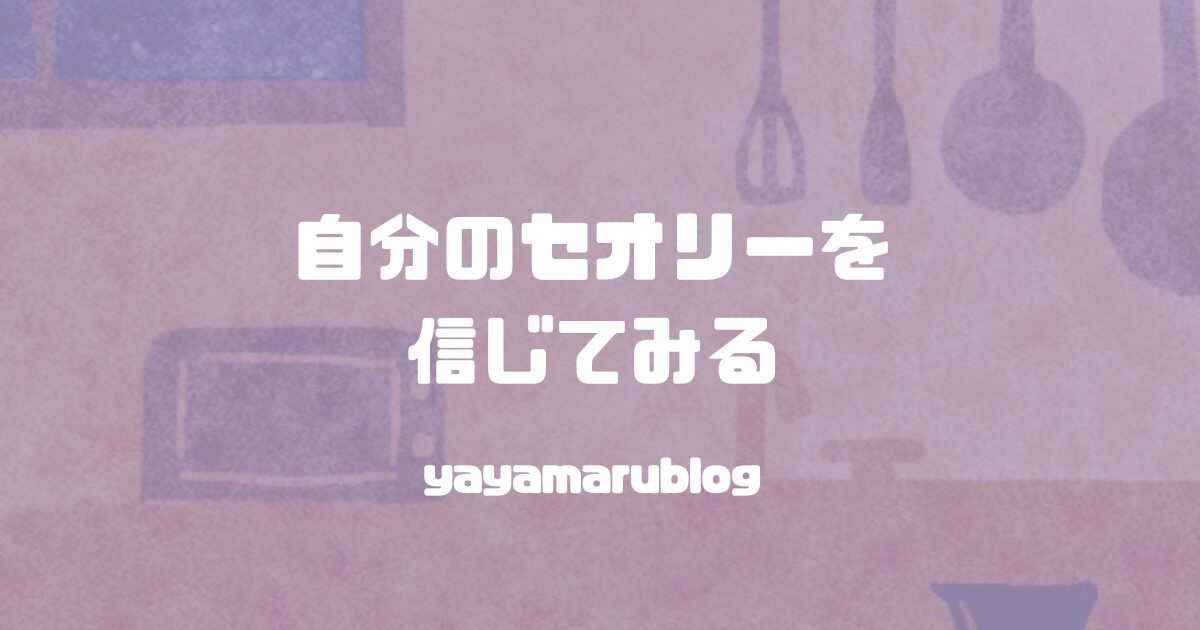

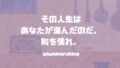
コメント