こんにちは、ややまる。 です。
日々、暖かさを肌で感じられるようになってきたなと感じます。
それと同時に、春は新しいイベントや寒暖差による環境の変化など、心も体もストレスに晒されやすい季節だなと思っています。
私もストレスを感じるとパニック発作を誘発しやすくなるので、日々研究や工夫を重ねています。
本日は私のパニック発作について大きな発見があったのでお話しようと思います。
ちょっと長めなので、先に結果と私がパニック発作に対して行った方法が知りたい方は、「電車に乗ってみた結果」を読んでください。
※症状がひどい場合には、一人で抱え込まずに医療機関やカウンセリングを活用してください。
- 私なりのパニック発作への考え方
- パニック発作と向き合う上で役に立った本
初めてのパニック発作
私がパニック発作を経験したのは、6年ほど前になります。
仕事の準備でシャワーを浴びていたら、動悸が止まらなくなり、初めて救急車を呼んだほどでした。
もちろん身体に異常はなく、隊員さんの優しい声がけのおかげで落ち着きました。
原因は過労です。
当時働いていた職場は不規則な時間での活動が多く、体が限界を迎えてしまい、初めて「このままじゃ、私、死んじゃうかもしれない。」と不安と恐怖で頭が一杯になっていたのを覚えています。
その後、業務中に動悸が激しくなってしまったり、寝ようとすると胸が苦しくなって眠れなかったり、当時一人暮らしでしたので、孤独死を本気で意識するくらいパニック発作に悩まされていました。
またお風呂に入っているときにパニックが起きてしまったので、トラウマになっていたのか、うまく入れない日がありました。
退職後、療養してからは症状はほとんど落ち着いたのですが、最近パニック発作がまた起こる場面が増えていました。
久しぶりの電車でパニック
今年の1月頃、所用で電車に乗る機会があったのですが、最寄り駅から乗った電車でパニック発作が出てしまい、途中下車を繰り返してようやく目的地へ辿り着きました。
しかもラッシュ時を避けて乗ったのですが、ラッシュ時の遅延の影響で何度も速度を落としての運行。
私の不安は爆発してしまい、「正直電車に乗りたくない。。。」と後ろ向きな気持ちが強くなってしまいました。
その日はなんとか用事を済ませ、帰りの電車に乗ったのですが、その時は発作は出ず最寄りまで途中下車なしで帰ることができました。
本来なら、電車に乗ることでパニック発作が出たので帰りの電車でも発作が出るはずです。
でも発作が出ることはなかったんです。
「あれ、なんで行きの電車ではあんなに不安だったのに帰りの電車は何ともないんだろう?」
不思議だなと思うと同時に、私のこのパニックには法則があるなと気づいた瞬間でした。
その後、私は自分のパニック発作について分析を始めることにしました。
パニック発作の根底にあるもの
まず私はパニック発作が起きている状況を整理しようと思いました。
私のパニック発作は以下の状況で起こっていました。
- 通勤ラッシュ帯の電車である
- 少し急いで息が上がっている
- 家から目的地に向かう電車である
- 一人で電車に乗る
上記の通り状況を並べてみたところ、ある共通点がわかりました。
それはどの状況下でも「安心できなくて嫌だ」という気持ちがありました。
- 通勤ラッシュ帯の電車である → 電車が止まる可能性があって安心できなくて嫌だ
- 少し急いで息が上がっている → 呼吸が落ち着かなくて安心できなくて嫌だ
- 家から目的地に向かう電車である → 大好きで安全な家から離れて安心できなくて嫌だ
- 一人で電車に乗る → 誰も頼れる人がいなくて安心できなくて嫌だ
安心ができないということは、常に不安な状態だということです。
そして私は用事の前日からパニックが起こるかもしれないという不安を大きくしていました。これは予期不安の症状です。
パニック発作は些細な不安がきっかけとして、特定の条件下で発作という形で出ているものだと思っていました。
ですが、パニック発作にも強弱があり、予期不安だけでなく日常の些細な不安を感じた時点でパニック発作は起こっているのかもしれないと思いました。
これは仮説ですが、私は日常的にパニック発作を起こしていたのでは?と思いました。
パニック発作が起こった時の対処法はあくまで対処療法、根本の治療には考え方を改めていく必要があるなと思いました。
そこから、根の考え方を改めるため調べていくうちに、とあるカウンセラーのブログと本に出会ったことでパニック発作との向き合い方のヒントを得ることができました。
動揺するから不安になるのかもしれない
とあるカウンセラーとは大嶋信頼先生です。先生は数多くのメンタルに関する本を出している現役カウンセラーです。
大嶋先生のブログ「緊張しちゃう人たち」もとても面白い視点でメンタルに感するアプローチをしていました。その中でも「動揺しなくなると自由になれる」こちらの記事が非常に大きな発見になりました。
そもそも動揺とは
大嶋先生の思う動揺の定義を以下の通りブログで説明していました。
「動揺」とは、他の作用で、動き揺れること。心や気持ちがゆれ動くこと。
パニクる、挙動不審になる。しどろもどろになる、あたふたする、平静さを失う、なんかが近い言葉で「それがなくなったらどんなに楽なことか」というやつです。
まさにパニック発作が起きている時の私だと思いました。
私のパニックは動揺からきていたのかと気づけた瞬間でした。
そして大嶋先生は動揺しないためには「私は動揺を許します。」と唱えてくださいと言います。
これだけだとピンと来なかったのですが、先生は書籍でパニック障害の患者について触れていました。そこに書いていることを読んで「私は動揺を許します。」の意図を理解できました。
ミルトン・エリクソン博士が行った催眠
大嶋先生の書籍では度々ミルトン・エリクソン博士のエピソードを紹介しています。
ミルトン・エリクソン博士(1901-80)はアメリカの精神科医・心理学者です。(以下、エリクソン博士と呼びます。)エリクソン催眠の考案者で、家族療法やNLP(神経言語プログラミング)等のモデルになっているとも言われています。
大嶋先生も、エリクソン博士から影響を受け催眠を勉強するに至ったとおっしゃるほどです。
また別の機会でエリクソン博士の催眠療法のおすすめ書籍の紹介できたらと思います。
今回のパニック発作に関連する内容として「無意識さん、催眠を教えて」という書籍のエリクソン博士のエピソードを紹介できたらとおもいます。
Kindle unlimited 加入者であれば読み放題対象になっています。(2025/06/02時点)
こちらでエリクソン博士は「逆説」という療法を使いました。
ここでいう逆説とは、本人の意思と逆方向のメッセージを無意識に送ることです。
エリクソン博士のエピソードでは、パニック発作を起こして倒れそうだと思った患者に対して「ここでなら倒れてもいいですよ」と言われたら、患者さんが倒れなかったというのです。
この逆説のポイントは本人の意思で考えていることを否定せず許すことにあります。
先ほどのパニック発作の患者は「ここで倒れてはいけない」という本人の意識に対して「倒れてもいい」という許しがあることで、力が入りすぎていた意識と無意識が適切な力で「倒れない!」という気持ちのイコールができたということなのではと解釈しました。
逆説の考え方が腑に落ちたので、実際に電車に乗って実践してみることにしました。
電車に乗ってみた結果
結論をいうと、発作なしで往復で電車に乗ることができました。
一応通勤ラッシュ帯を外しての実戦でしたが、これほど落ち着いて電車に乗れたのは久しぶりでした。嬉しい気持ちで満たされるかと思ったのですが、不思議とこれが普通だったと思うくらい淡々としてました。
実際に私が行ったことは、電車に乗る前から「動揺を許します」と唱えたり、ちょっと怪しいと思ったタイミングでもう一つの言葉を頭で唱えたりしただけです。
もう一つの言葉は「みんなも電車に乗るのが怖いんだよね」です。
これは私の孤立感に対する逆説の言葉です。
わたしのパニック発作の根底には、パニックを起こしてるのは「わたしだけ」という孤立感も後押ししていると思ったからです。個人的にはこっちの方が動悸を抑えてくれていた気がします。
みんなも怖いんだって気づくと、わたしだけじゃないもんねと妙に安心したのを覚えています。
今回の経験を経て、わたしのパニック発作は動揺と孤立感がメインで構成されていたことが大きな発見でした。
まとめ
パニック発作を起こさずに電車に乗れたという実績ができたことで、旅行したいという新たな夢ができました。
冒頭でも言いましたが、症状がひどい場合にはきちんと医療機関やカウンセリングを受けることも大切です。
ですが、自力でできることがないかなと探している人の力になれたら幸いです。
これからも癒しの観点で心理的な話を発信していきますので、見つけたらよろしくお願いします。
ここまで読んでくれてありがとうございました。
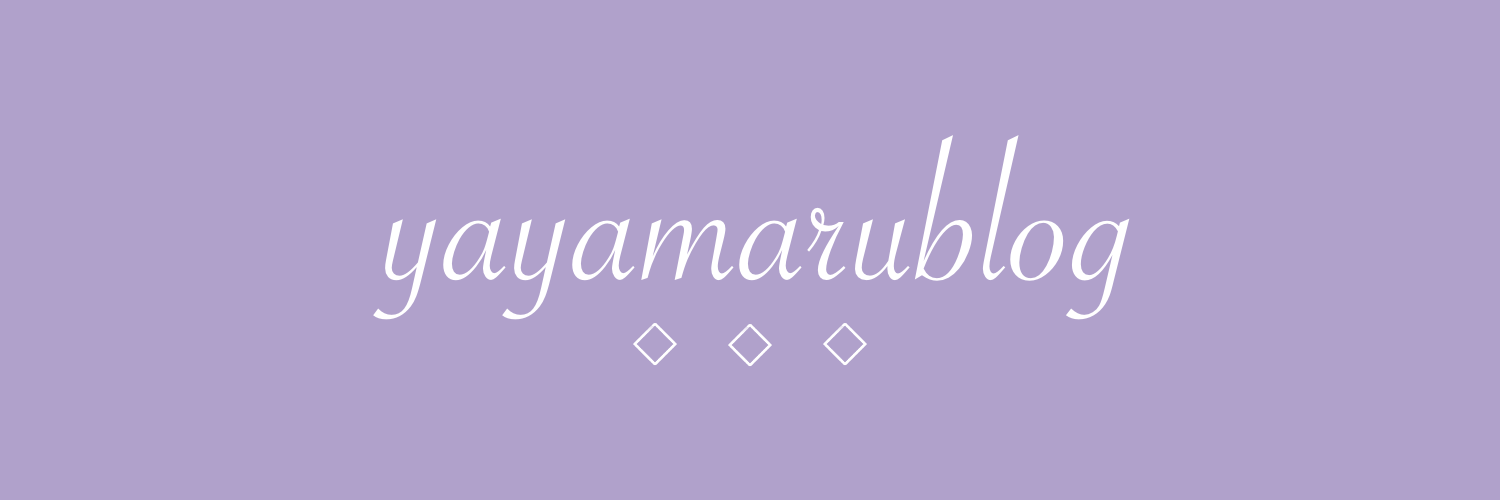
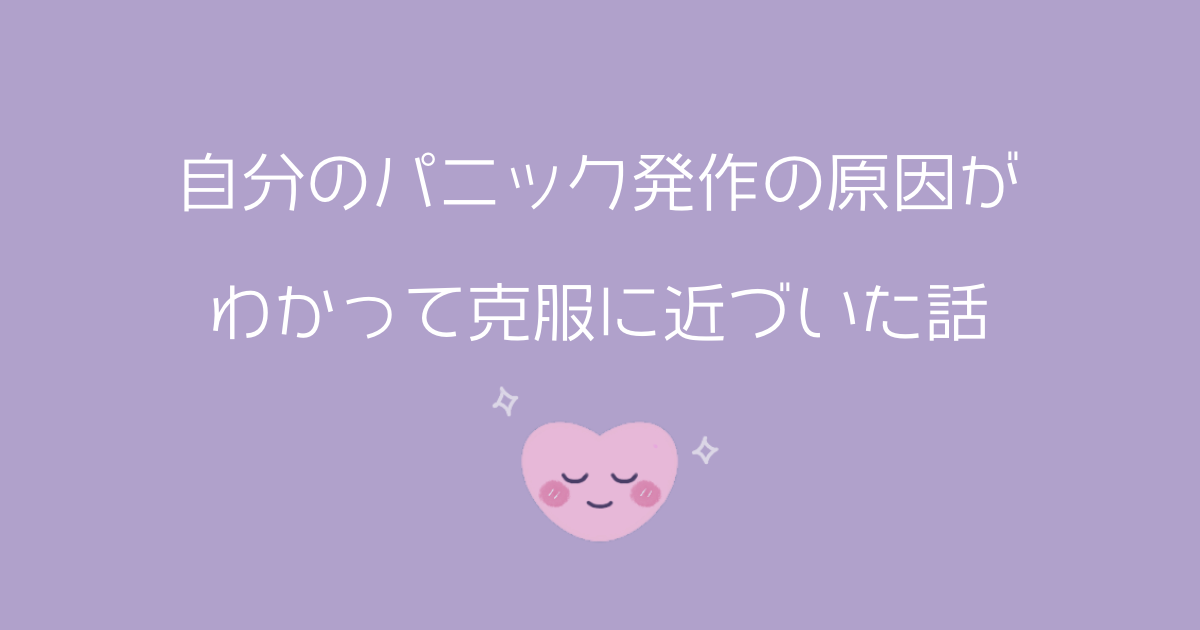

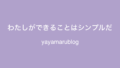
コメント